
出典:黄檗二祖 木庵禅師物語
発行:昭和57年10月隠元の法席を継いだ、萬福寺第2代木庵性瑫の生涯について記載しております。

出典:黄檗二祖 木庵禅師物語
発行:昭和57年10月隠元の法席を継いだ、萬福寺第2代木庵性瑫の生涯について記載しております。
 木庵禅師物語
木庵禅師物語急を聞いて馳けつけられた悦山和尚が、「どうかいま少し長くこの世に生きながらえて下さいますように」と申し上げられますと、 とかえって慰められました。辞世の句をお願いされますと、禅師は、 と言われ、しばらく側の者たちを眺めて...
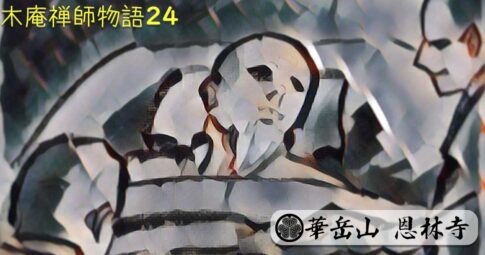 木庵禅師物語
木庵禅師物語天和四年正月十日、京都所司代稲葉公に侍者を使に出されて、永い間黄檗山のために盡力していたお礼を述べさせられました。十三日になるとにわかに病がぶり返し、皆なで秘かに医者を招いて診断を受けられるようお願いしましたがお許しにな...
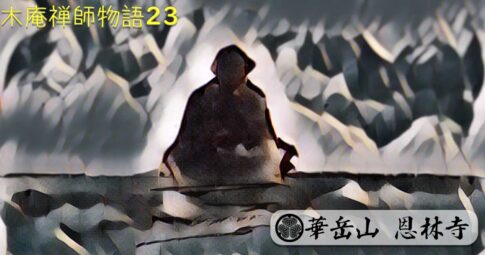 木庵禅師物語
木庵禅師物語慧林和尚に黄檗山第三代住持の席を継がさせられ、隠退されたとはいえ、それは名だけのことで、一日として安逸をむさぼられることなく坐禅され、また禅の悟りを求めて訪ねて来る者には親切に禅の真の姿を披露して接化されました。 そして...
 木庵禅師物語
木庵禅師物語七十歳を迎えられた延宝八年の正月三日、黄檗山の和尚方はお斎を設けて禅師のお誕生日に先だってお祝いをされました。 禅師は皆なの願いをききいれられ法堂に上り「寿生」の二字を主題にして説法されました。 十五日、冬の修行期が無事...
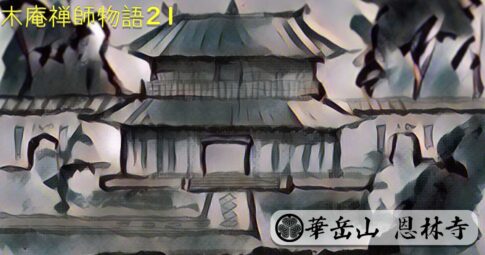 木庵禅師物語
木庵禅師物語延宝三年四月、隠元老和尚をお祀りする開山堂の棟上げ式が挙げられ、七月に入ると、萬寿塔院が開山堂の右側に建てられました。 同五年の秋には松隠堂の方丈を移し、四方に垣を築いて、開山堂や開山塔を守護するような形にされました。ま...
 木庵禅師物語
木庵禅師物語禅師が六十三歳を迎えられた延宝元年四月三日、黄檗開山隠元老和尚がお亡くなりになりました。 進龕、 掛真(肖像画を掛けてお祀りする)の法語を述べられました。 禅師は百ヶ日の間、寝床に休まれることなく、昼も夜もお棺の傍から離...
 木庵禅師物語
木庵禅師物語関東地方での黄檗宗の教線は日に日に拡がり、上野に萬徳山広済寺が潮音和尚によって建てられ、また江戸に紫雲山瑞聖寺が鉄牛和尚を住寺として迎えました。 寛文十一年四月、瑞聖寺の伽藍が竣工したのを機に、かねてから心にかけられてお...
 木庵禅師物語
木庵禅師物語寛文七年五月、将軍家から二万両と南海地方の木材チークが下賜され、仏殿を建てることになりました。 青木甲斐守が、黄檗山内に不二庵を新築してここに住まわれ、工事の監督にあたられました。 翌年、大雄宝殿(仏殿)の建築にとりかか...
 木庵禅師物語
木庵禅師物語寛文五年春、木庵禅師によって三壇戒会(当時、黄檗の独特な授戒の式)が開かれました。 これを機に甘露堂が東方丈の後方に創建され、禅堂の修覆、石畳を敷いた道路、二つの倉庫などが建てられました。 七月二十日、幕府から呼び出しあ...
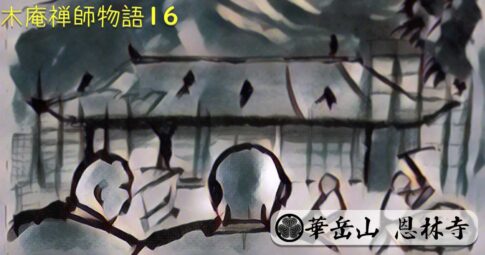 木庵禅師物語
木庵禅師物語この年の八月二十三日、禅堂が建ちました。 たまたま即非和尚がこの日黄檗山に登って来られましたので、冬の修行期には木庵禅師と即非和尚が東西両堂の首座として五百人近くの修行僧の指導にあたられました。 また、十二月には老和尚に...