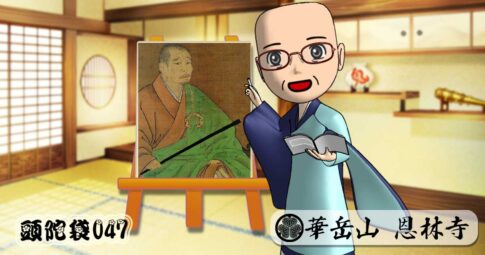お彼岸の話
私たちがお寺から頂く法要の案内には三仏会というものがあります。
この他に毎年、春と秋に行われる彼岸会、宗祖様を偲ぶ遠忌などがあります。
お彼岸は春分と秋分の日を中日として前後三日、それぞれの一週間をお彼岸と申し、いわば仏教週間であります。
この間、お寺ではお彼岸法要が行われ聞法に出かけたり、ご先祖様を偲びお墓参りをいたします。
この仏教週間はお盆とは異なり暦には載っておりません。
聖徳太子の時代から
お彼岸は農耕民族である日本にしか習慣はありません。
遠く聖徳太子の時代から伝えられてきたといわれています。
観無量寿経というお経の中に「日想観」という考えがあり、善導大師の教えに「その日、正東より出て真西に没す。弥陀の国土は日の没する処にあり。」とあります。
これを『観想』と言い、真西にある太陽を感じ、そしてかの世界を想う。
これが春秋の彼岸の由来とされています。
お供え
お彼岸の仏様へのお供えは春はぼたもち、秋はおはぎとなります。
ぼたもちは牡丹の花、おはぎは萩の花をイメージしています。
昔は、餅米、砂糖、小豆は貴重な物でこうしたもので作ったものをご先祖様を思い出しお供えし、また、家族みんなでおすそ分けする。
これこそ彼岸の教えである布施行の実践と言えるでしょう。
恩林寺涅槃会彼岸会法要
例年の通り、お馴染みの和尚様をお迎えして涅槃会、彼岸会を勤めます。
皆様ぜひお出かけください。
昨年お越し頂いた方々には改めてご案内いたます。
和尚の昭和下岡本を語る
私たちが育った戦後は食べる物もなくみんなが質素な生活をしていました。
学校帰りに田んぼの畔に生えた「スイモンサ」を食べたり、いったんだらけ「イタドリ」の茎を食べたりしました。
水浴びは苔川の雁川原さんの前あたりで泳いだり、時には隣村の冬頭の四十九院橋近くで泳いだりしました。
冬頭の川近くには岡本河童が現れ、キュウリ畑が被害にあいました。
当時の小瀬長十郎さん宅の前には、幅二尺ほどの川が流れており、シジミが採れました。
学校帰りに採って味噌汁に入れてもらったりしました。
そういえば大志多さんの裏に大野さんという家がありその横の川では青貝も生息、採れた時は大喜びで持ち帰り自慢しました。
私達の学校は北小学校で、建物は戦前のもので台風が来たりして倒れる心配があったのか、電柱よりもっと太い突支棒がしてありました。
西小学校の生徒に「わーい。ゴサ(田舎者)学校。つこ18本。」などと馬鹿にされました。
( 『つこ』とは突支棒のこと。)
今、思い出しても悔しい…。
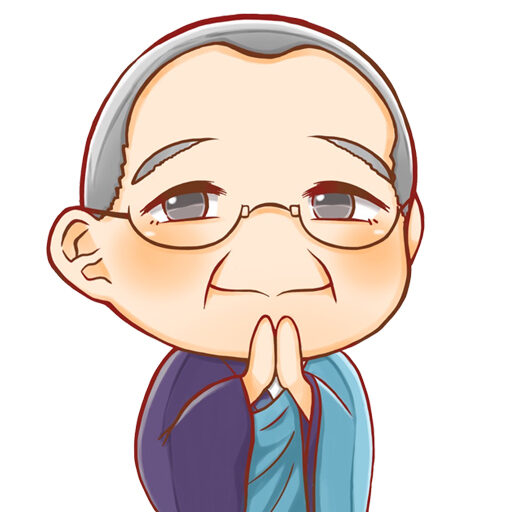
住職合掌

.jpg)