温かいお茶が落ち着く恩林寺の小僧です。
最近、高山にも色々な喫茶店が出来ています。
私はコーヒーが好きなので、以前カフェ巡りをしたことがありました。
一店一杯ずつ飲み、案の定飲みすぎでお腹を壊しました😅
喫茶去
仏教には「喫茶去」という言葉があります。
喫煙とお茶(コーヒー)と…去る?猿🐵?
私はそう思いましたが、実は文字通り読むようです。
「お茶を飲んだならばここから去れ!」お寺へ行ってお茶を頂いて…急に出ていけと言われたらビックリするでしょう。
実は中国の趙州和尚のお話が元になっているのです。
趙州和尚のお話
一人の僧侶が趙州禅師の元にやってきました。
趙州は、こう問いかけます。

はい、ございます。
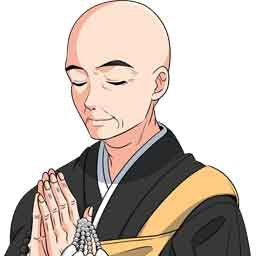
喫茶去!
後からもう一人の僧侶が趙州の元にやってきました。
趙州は、同じように問いかけます。
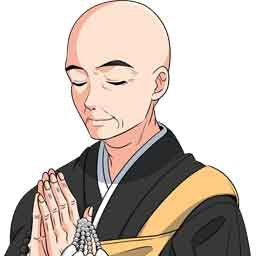
前にここ(趙州の寺院)に来たことがあるか?

いいえ、ありません。
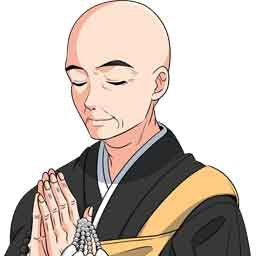
喫茶去
これは捉え方によって意味が変わります。
前者は、休憩したら修行へ旅立ちなさい!と諭しています。
それに対し、後者は、お疲れのようだからお茶でも飲みなさい!と癒しています。
現代では意味が簡略化され「まぁお茶でも飲んでいきなさい」という意味になっていった様です。
お茶🍵
お茶には色々な種類があります。
例えば、緑茶、紅茶、黒茶といったような色で分けられたり…。
他にも挽き方や蒸し方によって分けられたりします。
抹茶は茶臼で挽いて、粉末を溶かして飲むお茶で、茶道と聞くとこちらを連想される方が多い。
それに対し煎茶は摘んだ茶葉をそのまま蒸して作るお茶で、現在の一般家庭での飲み方です。
恩林寺でも美味しいお茶を出せるよう、私が頑張っていきたいです。
茶道
読み方が人によって異なっている『茶道』。
古くはチャドウ、現在ではサドウが一般的だと言われている様です。
主が客人にお茶を振舞い、客人は亭主のおもてなしを受け、お茶をいただくことを言います。
いただき方や礼の仕方などに色々な決まりがあり、これを作法といいます。
お茶と聞いて思い浮かぶのは、やはり千利休さんでしょうか?
歴史の教科書にも載っていて、わび茶の完成者。
茶聖とも称せられていますが、これは抹茶の世界の話。
黄檗宗でお茶といえば…もっと有名な方がお見えなんです😀
煎茶道
還俗した黄檗宗の元僧侶に、「売茶翁」という方がいます。
この人が極めた茶道を「煎茶道」といいます。
皆さんがよく飲んでいる緑茶などは、煎茶の中の一つです。
黄檗宗では、「茶頭」というお茶を点てる専門的役割があるほど、煎茶を大切にしています。
僕も茶道を習いましたが、一向に分かりません。
季節によって淹れ方も違うようで…奥深いものですね。
私はお茶を飲むと、心がホッとします。
皆さんも経験があると思います。
日本人はお茶と縁が切れない生き物なのかもしれません。

先々週に、怒りは6秒待てば抑えられるという話をしました。
心を落ち着かせることが大切なのです。
私は、毎朝のお勤めが終わった後に、温かいお茶を一杯頂いています。
その一杯は、ホッとすると同時に、今日1日のやる気を引き出してくれます。
喫茶去…お茶を飲んだのならば、日々の修行に取り組みなさい!
私も仕事に集中して頑張ります!
追伸:最近は喫煙が出来ないため、喫茶店というより、茶店だなと話している方がおられました😅小僧も納得です!
小僧合掌














前にここ(趙州の寺院)に来たことがあるか?